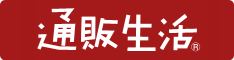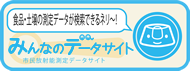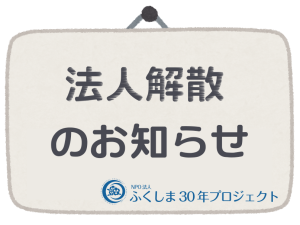© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.

南相馬市 自家消費の食品等の放射能簡易分析結果について 平成27年9月より
南相馬市の自家消費の食品等の放射能簡易分析結果の9月分から表を作成しました。【表01】
全体の測定件数は770件で、そのうち放射性セシウムを検出したのは466件(60%)、基準値である100Bq/kgを超えたのは182件(23%)となっています。単純に検出率だけを比較すると福島市よりも高めの傾向になっています。
平成26年9月の南相馬市の測定では102,900Bq/kgのマツタケがありましたが、今年は67,508Bq/kgのウシコタケが最高値となりました。他にも50,462Bq/kgのマツタケ、35,944Bq/kgのイノハナ(干)と昨年よりも高めの数値が並んでします。
南相馬市 自家消費の食品等の放射能簡易分析結果について 平成27年9月より【表01】
| 分類 | 品名 | 測定施設 | 採取地 | 放射性セシウム [ Bq/kg ] |
|---|---|---|---|---|
| きのこ類 | マツタケ | 石神生涯学習センター | 原町区馬場 | 50,462 |
| きのこ類 | イノハナ | 太田生涯学習センター | 原町区矢川原 | 3,986 |
| きのこ類 | イノハナ | 大甕生涯学習センター | 小高区羽倉 | 17,499 |
| きのこ類 | ハツタケ | 高平生涯学習センター | 原町区東ケ丘公園 | 7,430 |
| きのこ類 | イノハナ(干) | 原町生涯学習センター | 原町区矢川原 | 35,944 |
| きのこ類 | イノハナ | ひがし生涯学習センター | 原町区押釜 | 12,243 |
| きのこ類 | ウシコタケ | ひばり生涯学習センター | 原町区馬場 | 67,508 |
| きのこ類 | イノハナ | 鹿島生涯学習センター | 鹿島区橲原 | 25,091 |
| きのこ類 | シメジ | 小高区役所 | 小高区金谷 | 16,127 |
【表01】にある通り、9ヶ所の測定施設での最高値の検体は全て「きのこ類」となっています。また、福島市と同じようにイノハナが複数の測定施設で最高値を記録しています。
次に、種類別検出率の検出率です。【表02】
「きのこ類」に注目すると、セシウム検出率は98%、100Bq/kg超の検出率も89%とセシウムを検出する = 100Bq/kg超といった感じです。こういった「きのこ類」の検出傾向も昨年から続いていて、一向に下がる気配はありません。
また、この表の中で「その他の食品」が「きのこ類」についで高い数値を検出していますが、これは「きのこ類」の食品を茹でたり、干したりした物を指していますので、実質「きのこ類」が検出しているという事になります。
もう一つ、「果実類」も100Bq/kg超の件体がありますが、これは栗とクルミを果実に分類してあるためです。100Bq/kgを超えたのは、この2種類になりますので、これらを種実類として除くと果実類で100Bq/kgを超えた物はなかったようです。
種類別検出率【表02】
| 種類 | 測定件数 | 検出件数 | 100Bq/kg 超件数 | 検出率(%) | 100Bq/kg超 検出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米・加工品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いも類 | 42 | 14 | 0 | 33 | 0 |
| 豆類 | 25 | 4 | 1 | 16 | 4 |
| 野菜類 | 189 | 62 | 3 | 33 | 2 |
| 果実類 | 307 | 191 | 16 | 62 | 5 |
| きのこ類 | 158 | 154 | 141 | 98 | 89 |
| 肉類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚介類 | 4 | 2 | 1 | 50 | 25 |
| その他食品 | 44 | 39 | 21 | 89 | 48 |
種類別の検出分布を表に、そして、【きのこ類】についてはグラフにしました。【表03】【図03】
特に「きのこ類」については、1,000Bq/kg以上でさえ61.4%を占めていて、10,000Bq/kg以上も10.8%もあります。他に「その他の食品」も10,000Bq/kg以上の件体がありますが、これは先ほど述べたように「きのこ類」を加工した物です。
種類別の検出分布【表03】
| 種類 | 測定 件数 | 検出 限界値未満 | ND~ 50 Bq/kg未満 | 50~ 100 Bq/kg未満 | 100~ 500 Bq/kg未満 | 500~ 1,000 Bq/kg未満 | 1,000~ 5,000 Bq/kg未満 | 5,000~ 10,000 Bq/kg未満 | 10,000 Bq/kg以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米・ 加工品 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いも類 | 42 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆類 | 25 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野菜類 | 189 | 127 | 57 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 果実類 | 307 | 116 | 153 | 22 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| きのこ類 | 158 | 4 | 5 | 8 | 29 | 15 | 70 | 10 | 17 |
| 肉類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚介類 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| その他 食品 | 44 | 5 | 15 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 |
最後に、100Bq/kgを超えた「きのこ」の種類を上げておきます。
100Bq/kgを超えたきのこの種類 |
|||||
| ホウキモダシ | ホウキタケ | イノハナ | フウセンタケ | ハツタケ | アミタケ |
| マツタケ | カラスマイタケ | ウラベニホテイシメジ | ウシコタケ | カキシメジ | シメジ |
| キンタケ | イッポンシメジ | サクラシメジ | トキイロラッパタケ | ハタケシメジ | コウタケ |
| カジメ | モダシ | シモコシ | |||
南相馬市はセシウムの最高値しか発表していないので、具体的にどの種類の「きのこ」がどれくらいかという傾向が分からないのですが、上記のデータからも分かる通り、野生の「きのこ」については今後も放射能測定をして確認をしていかなければなりません。
昨年も書きましたが、日本には山菜、野生のきのこを食べるという田舎の文化があるのですから、ベラルーシを教訓にして、それらを測定してから食べるという習慣を根づかせなければなりません。
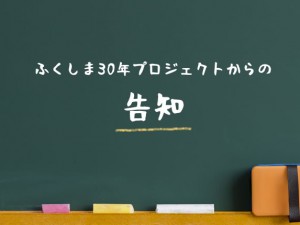
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…

【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
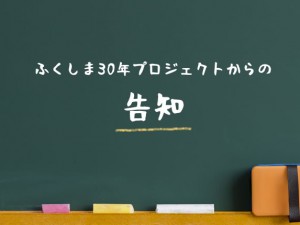
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…