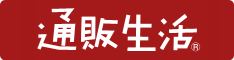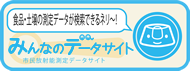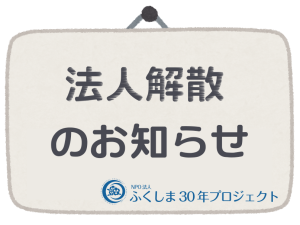© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.

ジャーナリズム? 政府広報?
飯舘村長泥地区で行われることになった、覆土無し除染土壌使用による食用作物栽培実証事業。それが判明したのは、大島堅一教授の行政文書開示請求によってでした。
報道後の大島教授の一連のTweetがまとめられていましたので、リンクを貼ります。
『除染の土 覆土せず野菜栽培をする実証事業へ 福島 飯舘』と行政開示文書からわかった事。問題指摘せずに政府の言説を垂れ流すのは報道ではなく広報機関(2020.8.10作成) – Togetter
大島教授はこれらのTweetのなかで、「行政が何か言うとそれを正しいと捉え、思考停止する人は環境省がやっていることを客観的に捉えられません。しっかり取材し、事実関係をみましょう」と言っています。
行政が何か言うとそれを正しいと捉え、思考停止する人は環境省がやっていることを客観的に捉えられません。しっかり取材し、事実関係をみましょう。とにかく腑抜けのメディアが多いのですが、共同通信の記事は正しく捉えています。地元でもまさか覆土無しとは思っていなかったんではないでしょうか。
— 大島堅一 (@kenichioshima) August 9, 2020
しかし、8月10日付の福島民報の一面トップの記事「除染土壌で農地造成 古里再生に思い寄せる」では、「覆土無し除染土壌による食用作物栽培実証事業」を行なった環境省に対しての批判の視点はなく、敢えて、そのことを無視したうえで書かれた記事でした。同紙が、共同通信の配信記事を掲載した二日後の記事だったのにも拘わらずです。
除染土壌で農地造成 古里再生に思い寄せる(福島民報) – Yahoo!ニュース
そして、この記事は一連の「復興を問う」という連載の一部なので、そのテーマから、地元住民の気持ちを丹念に拾うことに重きを置いています。それ故か、今回の環境省の行為には「除染土に覆土しない状態での生育実験も一部で始まった」と何の批判もありませんし、あまつさえ、記事の結びの手前に持ってきたことで肯定的な意味合いも持たせています。そして、翌11日付の記事「解除後でも除染して 風評…営農再開に不安」でも、引き続き覆土無しの件に触れますが、相変わらずその経緯は書かれておらず、読者に覆土無し栽培実証事業が既定路線に沿って行われていると思わせる内容です。
ここでもう一度、大島教授のTweetを引用します。
政府の言うことを右から左に流すのに慣れていると、ジャーナリストではなくなります。記者の皆さんはどこかおかしくなっているという自覚を持った方が良いです。私は違うと無反省に言える人は、きっと自覚なき病にかかっているのだと思いますよ。
— 大島堅一 (@kenichioshima) August 9, 2020
福島民報は共同通信の配信記事を一面に掲載しただけに非常に残念ですし、これらの記事を目にしたときは、その落差に愕然としてしまいました。共同通信の記事では、すでに覆土無しで栽培実証事業が行われた問題点が指摘してありましたし、それを全文掲載した福島民報が、その問題点を把握していないはずはありません。
福島民報は共同通信との配信契約の上で掲載しただけではなく、敢えて一面に掲載するという編集権を行使したわけですから、自社の独自記事も政府広報ではなく、ジャーナリズムを目指していただきたいと思います。
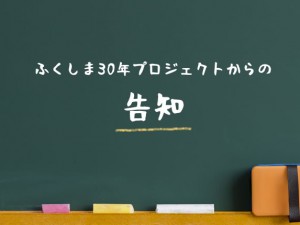
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…

【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
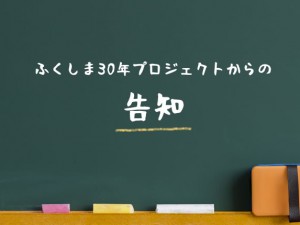
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…