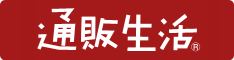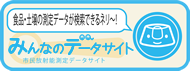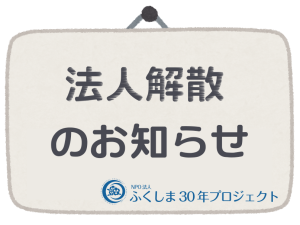© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
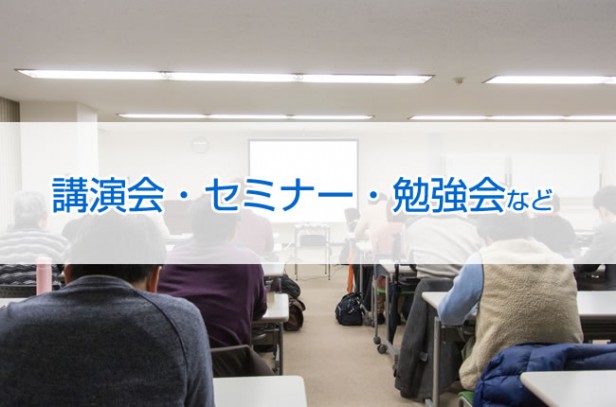
2016年1月23日(土) 西東京市で行われた公開講座 『放射能汚染と向き合うための基礎知識』に参加して
2016年1月23日(土)
東京都西東京市で行われた公開講座
『放射能汚染と向き合うための基礎知識』
に参加してまいりました。
会場は満席で、立ち見の方もいる程でした。

講師は京都大学原子炉実験所助教の今中哲二さんです。
今中さんは、原子力工学の専門家として原発の危険性警鐘を鳴らし続け、福島原発事故前からチェルノブイリ事故についてずっと調べていらっしゃいました。
その経験を活かし、3.11以降市民に解りやすい講演等で活躍しています。
今回の講演会の前半は、原子力発電所の仕組みから始まり、放射能の基礎知識(放射線、放射能、放射性物質の違い、シーベルト、ベクレルの単位の違いなど)
そして、放射能汚染と被曝の現状などについてのお話でした。
講演会の後半は、今中さんと福島にもよく来て下さっている山田真先生(子どもたちを放射能から守る小児科医ネットワーク代表)との対談の予定でしたが、急遽私も入ることになり鼎談となりました。
山田先生が、初期に福島で健康相談会を開いた時の印象から、この五年間での変化。
私も福島で子育てをしながら暮らしている立場、また、初期から測定を続けている立場としての、福島の現状をお話しさせていただきました。
会場からも、閉会の時間がきても質問が止まず、会場使用ギリギリまで延長の会となりました。
『放射能汚染の中で暮らすということ =
どの程度の被曝ならガマンするかを決める事』
考えれば考えるほどその通りだと納得してしまいます。
希望の持てるお話しが多々あった中で、印象に残った、深い言葉でした。
さはら まき
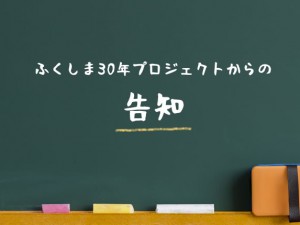
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…

【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
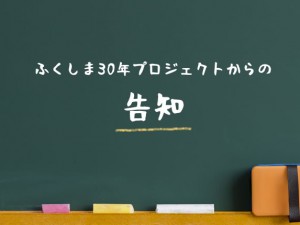
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…