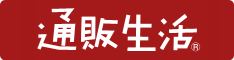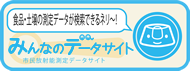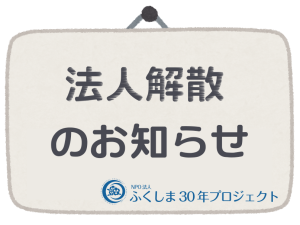© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
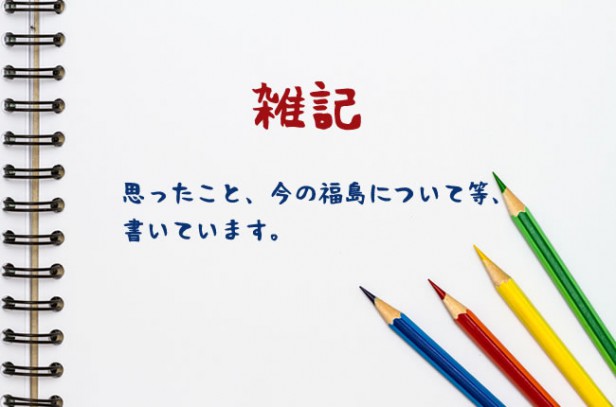
わらじまつり
昨日の東北六魂祭パレードのTV中継を観たが「わらじまつり」の酷さが際立っていた。
段取りが悪い、地味、演者のノリ等々。
途中、観客にカメラが振られるのだが、皆一様にシラケていた。
その次の「花笠まつり」が始まると再び観客も盛り上がり始め、モニターを通して観ているこちらも一安心するという感じだった。
このように東北六県の祭りが一様に並ぶ機会があると、そこに県民性も表れているように見える。(福島の場合は、よりミニマムに福島市の市民性でもいいかもしれない)
何か今回の事故からの一連のゴタゴタがこの「わらじまつり」の演目の企画に出ている。
ひょっとしたら、女川原発が事故を起こした場合、宮城県住民の対応は福島とは違う展開になったかもしれないと思わせるものがあった。
宮城県の場合は「七夕まつり」になるわけだが、これも「わらじまつり」と違って見る物を楽しませるように工夫がされていた。この六魂祭用に味付けされた物があったと思う。
しかし、「わらじまつり」にはそれがなかった。
いつもの「わらじまつり」があるだけだった。
福島の人間なら誰でも「わらじまつり」について思い浮かべる「地味」という印象を、この六魂祭には積極的にアレンジして変えていくべきだったのだ。
しかし、そういった積極性がなかったように見える。
そしてふと思った。
これが今回の事故における住民達の対応にも表れているのではないか、と。
例えば、どこの地域で事故が起こっても、福島のように様々な軋轢等々、問題は起こると思う。
しかし、今の福島のようなゴタゴタに至ったのは大半の住民の態度が受け身・消極的、そして事の本質から目を逸らして小手先での対処で済まそうとしたからではないか?<
今日の「わらじまつり」の演目を観てパッと思いついた。
あの「わらじ音頭」は今の福島を象徴している。
(あべひろみ)
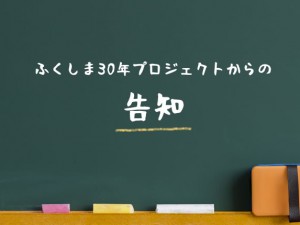
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…

【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
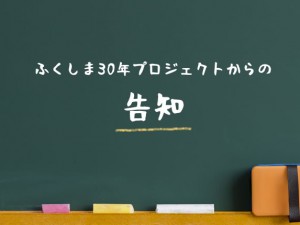
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…